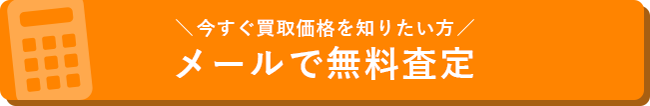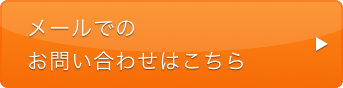金本位制とは?歴史、メリット・デメリットを簡単に解説| 創業大正9年の須賀質店
金本位制とは、通貨の価値を金で裏づけ、紙幣がいつでも金と交換できるようにした制度です。金本位制は、インフレや為替変動への耐性があるというメリットがある一方、非常時に通貨供給が硬直化するというデメリットもあります。
この記事では、金本位制の日本と海外の歴史や現代の影響などを紹介します。また、管理通貨制度との違いや、いつ廃止されたのか、復活した場合の金資産に与える影響についても解説しますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

創業100年の実績から、熟練査定士による業界最高値をご提示致します。
金本位制とは?
金本位制とは、通貨の価値を金で裏付け、紙幣を一定比率で金と交換できるよう定めた通貨制度です。金準備に応じて通貨発行が制約され、為替安定とインフレ抑制を狙う仕組みとされ、近代の国際体制で広く用いられました。
仕組み
各国は、通貨と金の交換比率(平価)をあらかじめ定めます。中央銀行は、その比率を守るために金を事前に準備として保有し、紙幣を金と交換したいという請求にいつでも応じられるようにします。紙幣の発行量は、保有している金の量にあわせて自動的に制限されます。国際的には、各国の平価に基づいた固定相場制が機能するため、為替は比較的安定しました。貿易赤字の国では、金が流出して通貨量が減り、物価が下がる一方、黒字の国では金が流入して通貨量が増え物価が上がるため、収支は自然に調整されます。
歴史【海外と日本の動き】
金本位制は、19世紀後半にアメリカやヨーロッパで広がり、日本では1897年に本格採用されました。ここでは、海外と日本それぞれの金本位制の歴史について解説します。

金本位制の導入
【海外】1816年のイギリスが金本位制を始めたことをきっかけに、多くの国で採用されるようになりました。19世紀末にはロンドンを中心に国際的な仕組みとして確立し、貿易や資金のやり取りが円滑に進むようになりました。
【日本】明治政府はまず銀本位制を採用し、円の価値を担保しました。その後、日清戦争の賠償金を活用して1897年に金本位制を採用。1円=金0.75gと定め、円の信用が高まり国際的な取引がしやすくなりました。第一次大戦中の1917年に金の輸出を禁止し、1930年に再び解禁しました。
世界恐慌による金本位制の崩壊
【海外】1929年の世界恐慌で経済が悪化する中、各国は金を守るため緊縮策を取りました。1931年にドイツの銀行破綻を受けてイギリスが金本位制を停止し、ポルトガルや北欧諸国、アメリカも金との交換を停止していきます。フランスやオランダなども1936年には停止し、国際的な金本位制は完全に崩壊しました。
【日本】1930年に旧来の交換比率のまま金の輸出を解禁しましたが、すでに世界恐慌が始まっており、金が海外へ大量に流出。景気が一層悪化したため、1931年12月に金の輸出を再び禁止し、金本位制から離脱しました。
管理通貨制度への移行
【海外】金本位制崩壊後、各国は金との交換をやめ、中央銀行が通貨量を管理する「管理通貨制度」に移りました。第二次大戦後はドルを基準通貨とするブレトンウッズ体制が成立し、一次復活しますが、1971年にアメリカがドルと金の交換の停止を宣言(ニクソン・ショック)。1973年に変動相場制へ移行しました。
【日本】1931年の離脱後、管理通貨制度の下で信用政策と為替管理を強化してきました。戦後は1ドル=360円の固定相場となり、円安効果で輸出が伸びて経済復興が進みました。しかし1971年のニクソンショックによりブレトンウッズ体制が崩壊し、1973年に現在の変動相場制へ移行しました。
金本位制の種類
金貨本位制とは
金貨本位制は、金貨が実際に流通し、金貨と紙幣を自由に交換できる、もっとも古典的な形態です。金貨がそのまま通貨として使われ、紙幣を持っていれば銀行でいつでも金貨に替えることができました。19世紀から20世紀初頭にかけて欧米各国で広く採用され、通貨の価値が実物の金で直接裏づけられるため信用度が高く、国際貿易でも安心して取引できるメリットがありました。ただし、金貨の鋳造や流通管理にコストがかかり、金の保有量が通貨供給を制約するというデメリットもありました。
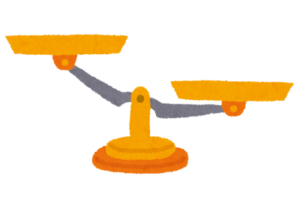
金地金本位制とは
金地金本位制は、金貨の流通をやめ大口の金塊(インゴット)のみ、紙幣を交換できる仕組みです。第一次世界大戦後、金の流出を抑えたい国で多く採用されました。一般の人々が少額の紙幣を金に替えることは難しく、一定額以上でなければ交換に応じないため、実質的には大企業や富裕層、政府機関だけが利用できる制度でした。これにより金の国外流出を抑えつつ、形式上は金本位制を維持できましたが、一般国民には恩恵が少なく、金本位制の理念からは後退した制度とされています。
金為替本位制とは
金為替本位制は、自国通貨を金ではなく金本位制を採用する他国の通貨(基軸通貨)と交換できる仕組みです。金の保有が少ない国が採用し、ドルやポンドなどの主要通貨を準備して自国通貨を発行しました。金を直接保有する必要がないため、導入しやすい反面、基軸通貨国の経済状況に左右されやすい弱点がありました。

創業100年の実績から、熟練査定士による業界最高値をご提示致します。
金本位制のメリット
為替レートの安定
各国が通貨と金の交換比率を固定していたため、国際的な為替レートが安定しました。例えば1ポンド=金○グラム、1ドル=金○グラムと決まっていれば、ポンドとドルの交換比率も自然に定まります。
為替相場が大きく変動しないため、海外との取引で将来の為替リスクを心配する必要が少なく、企業は安心して輸出入の計画を立てられました。

インフレの抑制
紙幣の発行量が金の保有量に制約されるため、政府は無制限に通貨を発行することができません。金という実物資産が通貨を裏づけているため、通貨の価値が下がりにくく、物価の急激な上昇が抑えられインフレ抑制につながりました。
この仕組みが通貨への信頼を支え、経済の予測可能性を高める効果がありました。
貿易の活発化
為替が安定し通貨の信用が高まったことで、国際貿易が大きく発展しました。各国の通貨が金を通じて結びついていたため、遠い国との取引でも通貨の価値を心配する必要が少なく、商人や企業は積極的に海外市場へ進出できました。
決済も金で行えるため、貿易相手国の通貨を信用できない場合でも取引が成立しやすく、19世紀から20世紀初頭にかけて世界経済が大きく成長する基盤となりました。
金本位制のデメリット
経済の状況に対応できない
金本位制では紙幣の発行量が金の保有量に縛られるため、不況時に通貨を増やして景気を刺激することができませんでした。政府が経済対策で公共事業を増やしたくても、金が足りなければ資金を調達できず、失業や倒産が増えても有効な手を打てません。
柔軟な金融政策が取れないため、景気の波に合わせた調整ができず、経済が硬直化しやすいのが最大のデメリットです。
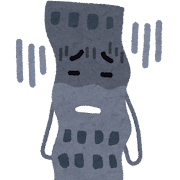
景気後退の長期化リスク
不況で物価が下がると、人々は「もっと安くなる」と期待して買い控えるため、さらに需要が減って物価が下がり続けるデフレスパイラルに陥りやすくなります。
金本位制では通貨供給を増やして需要を刺激できないため、一度デフレが始まると抜け出すのが非常に困難でした。世界恐慌では多くの国がこの罠にはまり、長期間にわたって深刻な不況が続く原因となりました。
貿易赤字による金流出
貿易で赤字が続くと、不足分を金で支払うため金が国外へ流出します。金が減ると通貨の発行量も減らさなければならず、国内の資金が不足して企業活動が停滞し、さらに景気が悪化する悪循環に陥りました。
金を守るために金利を上げると投資や消費が冷え込み、国民生活が圧迫されるという問題もありました。
金本位制と現在の通貨制度の違い
管理通貨制度
現在の主要国が採用する管理通貨制度は、金との交換を保証せず、中央銀行が経済状況に応じて通貨の発行量や金利を調整する仕組みです。紙幣は金ではなく中央銀行の資産や国の信用を根拠に発行されます。
金本位制と違い、不況時には通貨を増やして景気を刺激したり、インフレ時には通貨を絞って物価上昇を抑えたりと、柔軟な政策対応が可能です。ただし政府が過度に通貨を発行するとインフレのリスクがあるため、中央銀行の独立性と適切な運営が重要になります。

BRICS共通通貨
BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカなど)諸国は、ドル中心の国際通貨体制から脱却するため、共通通貨の創設を検討しています。加盟国間の貿易決済で自国通貨や共通通貨を使うことで、為替リスクやドル依存を減らす狙いがあります。
実現すれば金本位制の要素を部分的に復活させる可能性がありますが、加盟国の経済規模や政治体制が大きく異なるため、実現には多くの課題が残されています。

価値が衰えない金
多くの国が金本位制を廃止し、現在は管理通貨制度に移行していますが、金の価値は衰えることなく上昇を続けています。世界的な金融不安や地政学リスクが高まるたびに、金は「安全資産」として買われ、価格は長期的に右肩上がりの傾向を示してきました。
上記のグラフは、金価格の毎年の平均価格推移です。2018年と比べて約3.4倍になっていることがわかります。2025年10月現在も金価格は高騰を続け、1グラム2万3千円を超える水準に達しています。

まとめ
金本位制は通貨を金で裏づける制度で、為替安定や物価抑制のメリットがありましたが、不況時に柔軟な対応ができず世界恐慌で崩壊しました。現在は管理通貨制度に移行し、中央銀行が経済に応じて通貨を調整しています。
制度は廃止されても金の価値は上昇を続け、安全資産として世界中で重視されています。金を持つ方にとって、歴史を知ることは資産価値を見極める重要な手がかりとなるでしょう。

金の買取に関する最新記事

一オンスとは、貴金属の国際的な計量単位で、1トロイオンスは31.1035グラムと定義されています。金投資や海外の金価格表示で目にする単位ですが、正確な換算方法や価格変動の仕組みを理解している方は意外と…もっと見る

「金価格2倍になるという予測は、本当?」「金の価格ってこれからどこまで上昇するのだろう?」——金を保有している方も、購入を検討している方も、このような疑問をお持ちではないでしょうか。結論として、金価格…もっと見る

K18YGとは、「18金イエローゴールド」を意味し、金とその他の金属を混ぜた合金の一種です。純金75%を含む高品質な貴金属として、婚約指輪やネックレスなど幅広いジュエリーに使用されています。この記事で…もっと見る

金の見分け方は、刻印、色見、重さ、磁石、水、試金石、剥離の確認、そして査定に出す8つの方法があります。手元のネックレスやブレスレット、指輪が「本物の金なのか、それとも金メッキなのか」を知りたいと思った…もっと見る

18金と24金の違いは、金の含有率です。24金は純度99.9%のほぼ純金で資産価値が高く、18金は金75%に銀や銅を混ぜた合金で、傷に強く日常使い向けです。同じ重さでも24金のほうが価格は高く、耐久性…もっと見る
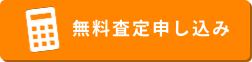
 査定依頼
査定依頼  店舗一覧
店舗一覧